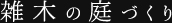HOME>雑木の庭つくり日記
全国メガソーラー問題シンポジウム開催のお知らせ 平成30年8月16日

ここは、房総半島南部、千葉県鴨川市の山中です。
この地域は三浦層群と言われる、力のある岩盤層によってとても豊かな森が太古から保たれ、それが素晴らしく豊かな生態系を育み、力のある水が湧き出してふもとの暮らしを千年万年と支え続けてきました。
今やここは、千葉県内では最も生態系豊かな森の一角と言えるでしょう。
この山の頂部一体、300ヘクタールという見渡す限りの広大な範囲の木々を伐り、総延長3キロメートルという広大な範囲で尾根を削り取り、谷を埋めて、造成される、日本最大級のメガソーラー(大規模太陽光発電設備)建設の計画が進んでおり、今回、その計画地踏査にうかがいました。

計画地とその周辺一帯の山域に無数の谷が刻まれ、そしてそこには川底からも山襞からも湧水が染み出し、それが今もなお、渓流の魚やカジカなど、今や貴重な川の生きものを育みます。
ひとたび山が削られると、山が本来保ってきた貯水機能、洪水調整機能、浄化機能も失われます。
森が水を貯えなくなった分、こうした大規模開発においては造成の際、表面を流れる水をいったん蓄えて調整する、巨大な調整池がいくつも建設されます。
集落の水源になっているこの沢の上流部に調整池が建設され、そしてその排水はこの沢に放たれます。
千年万年にわたってこの地の豊かな暮らしを支えてきた要の地形を根こそぎ削ぎ取って、未来にわたって不毛の地にしてしまう、このとんでもない計画が見直されることを願い、こうした現実を多くの人に知っていただきたいと願います。
同時に、仮に計画が始まってしまったその後も、こうした、周辺河川の環境変化を観測し、そしてそれをきちんと伝えていき、全国の、そんな思いで今回、周辺環境調査地点の視察に入ったのです。

時折強く降り注ぐ雨の中、この杜の母のような大木たちの霊気に打たれながら歩きます。
小さな尾根や露岩の上に、モミの巨木が点々と見られ、その周辺は林床に至るまで、ひと際豊かな森の様相を呈します。杜の主木として巨木となったモミの木が、マザーツリーとなって森を育んでいるのでしょう。
それにしても、房総半島の極相林(その土地の風土環境が到達する森の最終形態)において、林冠の最高木として、細かな起伏の高みにはかつてはモミの木がこうして点在していましたが、今、そんな豊かな森はもう、房総ではこの山域から続く三浦層群一帯のほかにはないことでしょう。

高木、中木、低木、そして林床の幼木、下草、土の中の菌類微生物たち、その豊かな営みがこれまでそれこそ数千年以上もの暮らしの環境を支え続けてきたのです。
世界有数の人口密度を支え続けてきた、限りなく豊かだった日本の国土、その75%は山地であって、人間の大半は今、平野部に暮らし、そして社会インフラの多くもまた、平野に集中します。
その平野の暮らしの安全と豊かさ、生産力も資源も、いのちの水も、空気も、そして快適で暮らしやすい微気候をも、永遠に生み出し続けてきたのが、一見経済価値がないように見られてしまう、この山地における豊かないのちの営みにあるのです。
かつてはこの山の営みを守るため、要の樹木をご神木とし、環境の要を鎮守の杜として守り、そして水の湧き出しに龍神を祀り、そうして先人の懸命な努力によって、世界有数の人口密度を抱えながらもなお、この国は豊かな環境を今に繋いできたのでした。

尾根筋に達すると、とても心地よい風が吹き上げて涼しく、大木が点在する森はまた、この土地の長年の営みを物語ってくれるようです。
さっきまで地下足袋にたくさん吸い付いてきたヒルも、心地よい尾根の環境には全くいなくなります。
不快な環境を招いてしまったのは基本的に人間に寄る環境の錯乱による部分があまりに大きく、ヒルも、荒れてしまった環境の叫びのように湧き出してくるもののように思えます。全てを壊してしまう人間を寄せ付けないための、大地の反応として、現れ、そして良い環境を保つ、例えばふかふかの苔むしたマザーツリーの根元や安定した尾根筋頂部などには、ヒルは全くいなくなります。
そう思うと、人の営みと言うもの、そして自然の意志、そんなことをもっときちんと感じて、その法則の中に生きるすべを次世代に向けて知恵を絞って見出していかねばならないように思います。

今歩いているこの尾根も、最大で標高40mにわたって削り取って平坦化し、そしてその土で深い谷を埋め、そして跡形もなく地形を変えたその上に、50万枚もの巨大なソーラーパネルが並ぶ、そんな計画が今にも動き出そうとしているのです。

そして、奥に見渡す尾根筋もすべて削り取って平らにし、地域の水源となってこれまで集落の暮らしを支えてきた尾根の手前の深い谷も、高さ80mもの高さで埋め尽くされようとしているのです。

大切な山林の開発はこれまでも様々ありましたが、メガソーラーはそれらとは全く違う規模で、しかも壊して話いけない山地頂部もかまわずに行われるという点で、これまでの開発とはそのインパクトは比較にならず、それによって生じるであろう国土環境の劣化がどれほどの規模で広がってゆくか、想像もできないことでしょう。
いや、もうすでに全国で様々な問題が早速起こり始めておりますが、まだそれは、ほんの始まりに過ぎません。
それほどまでに、この開発はこれまでにない、未曽有の破壊につながる危険をはらんでおります。
大規模造成事業の経済効果の高さも大きな後押しとなって、国策で強力に進められるメガソーラー事業、電力の需給に関係なく発電すれば、固定価格で必ず売却でき、そして大きな利益が見込めるメガソーラー造成の圧力は凄まじい勢いで、このまま放置すれば数年で国土はまるで別のものになり果ててしまう、そんな危険すら感じております。
今、この現実を多くの人に知っていただき、身近な問題として放置できないことを多くの人と共有していかねばならないと感じます。
西日本豪雨に広域被害もあり、今国土防災の在り方も問い直されております。
そんな中、メガソーラー造成含む太陽光発電設備造成のもたらす現実に、多くに人が気づき始め、全国各地で、計画地地元による反対運動が日増しに勢いを増してきました。
反対賛成の二項対立ではなく、ただ単に、土地を生産力を未来永劫に修復不可能なまでに奪ってしまう今のメガソーラーは絶対にまずいということ、一時の繁栄のためにいのちの営みの根幹をここまで奪ってはいけない、そのことを基軸に、未来の暮らし方、文明の在り方へと力を合わせて方向を共有できればと願います。
本質は、自然環境の健全化なくして、本当の安全も安心も、決して得られないということ。そのことを、声を大きくして伝え続けたいと思います。
共感の輪を広げていき、少しでも早く、メガソーラー増設の波を収めていきたい、そう思います。
今、全国で急速に広がるメガソーラーの問題を訴える各地地元の声を、大きな輪として伝えてゆくべく、来たる10月8日に急きょ、全国メガソーラー問題シンポジウムを開催することになりましたので、取り急ぎ、下記にご案内いたします。
~全国メガソーラー問題シンポジウムのご案内~
日時;2018年10月8日(体育の日)
場所; 長野県茅野市(中央本線特急停車駅)
第一部;茅野市市民館コンサートホール(定員300名)
第二部;茅野ユイワーク 情報交換会・質問・お話し会
参加費;無料
主催;全国メガソーラー問題シンポジウム準備委員会(事務局;小林峰一)
タイムスケジュール;
12;30 開場、受付開始
13;00 開演挨拶及びお話し
「そもそもソーラーがなぜここまで増えたのか」(仮称)
佐久裕二氏(10分)
13;10 基調講演① 「メガソーラーが環境を壊す10の理由」40分間
高田宏臣(環境活動家、造園家)
13;50 基調講演② 「メガソーラーを止める10の方法」30分間
梶山正三氏(弁護士)
14;20 休憩(10分)
14;30 各地メガソーラー計画地における住民活動事例報告と現地からのご意見
*4か所ほど、各20分程度、報告していただき、様々な地域の問題と取り組みを学びます。
15;50 総括、まとめ(各報告者のコメント)
16;00 第一部終了 第二部会場(茅野ゆいわーくに移動)
16;30 第二部 情報交換、意見交換、お話し交流会
*お茶お菓子は用意いたします。アルコールの持ち込みはできません。
お話ししたいことがある方、各地の報告、活動紹介、質問もざっくばらんに承りながら、この場で交流を兼ねて、それぞれが次への展望へとつながるような、有意義な交流会になればと思います。
18;00 第二部終了 解散
18;30 懇親会(会場未定。事前申し込み制となります)
シンポジウム参加は事前申し込みは必要ございませんが、懇親会は事前申し込み制となります。詳しい案内は追って公開いたします。
*なお、今回の開催地となる茅野市は、霧ヶ峰山麓に計画中の諏訪市四賀ソーラー事業地の下流域にあたります。
地元の住民団体「米沢地区Looop対策協議会」の方々の全面的なご協力、ご賛同の上、シンポジウムが開催されます。
この後、第2回シンポジウムは今のところ、千葉県鴨川市「鴨川の山と川と海を守る会」の方々が名乗りを上げてくださっております。
これをスタートに、この問題の本質を知っていただき、考えていただき、その関心の高まりのきっかけになればと思います。
また、こうした集いが各地域で活動される地元の方々の励みや力になる、そして、この問題に対する風向きを変えて、良い方向に向かう原動力になればと思います。
多くのご参加、多くの方の関心が、この問題を鎮めてゆく力になります。どうか、一人でも多くのご参加を、心からお願い申し上げます。
投稿者 株式会社高田造園設計事務所 | PermaLink
呼吸するコンクリート駐車場をつくる。 平成30年8月11日
皆様お久しぶりです。高田造園設計事務所の高田です。今年は公私に多忙を極め、数か月ぶりのブログ更新となりました。
気づいたらもう何か月もまともな休みの日はとれておらず、ようやく明日からお盆休みに入ります。21日まで10日間のお休みをいただきます。
私自身はお盆中もすべきことが山ほどあり、ほぼ毎日活動しておりますが、3日間程度は子供と山登りに行く予定でおります。溜まりに溜まった心の塵をきれいに落とし、また怒涛の後半期、天地人、現代未来に対し、意義のある仕事に努めたいと思います。
これでようやく今年の前半期終了となります。
高田造園、そして私たちの環境活動に関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。
また、工事や手入れを長らくお待ちくださっている方々、大変恐縮でございます。
お盆明けにまたご連絡いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日、千葉県佐倉市で施工中の旧家敷地内車道および駐車場工事が植栽を残してほぼ終了しましたので、過程を報告させていただきます。

8年前に竣工した旧家Aさんの庭、家屋建て替えに伴って痛んだ環境の再生および駐車場、車道工事が大方終了しました。

車道部分はコンクリートの洗い出し、そして玄関前の3台分の駐車スペースは、コンクリート盤および洗い出しと、コンクリート工事です。
「高田造園がコンクリート使うの?」と思われる方が多いでしょうが、高田造園のコンクリート施工は、コンクリートの下で、しっかりと樹木根も微生物活動も健全におこなわれて、しっとりとした大地の呼吸も根の動きも妨げない、徹底して、そんな配慮と工法を考え、施工します。
従って、真夏の日中、日差しを浴びたコンクリート表面も、生きている下地土壌からの冷気できちんと冷却されます。また、下地の土を全く痛めないため、コンクリートと言えども微妙なクッションが働き、足も疲れない。
その上、下地にしっかりと根が張り巡らせてゆくため、地盤は本当の意味で安定し、よい環境が持続します。
今、街も里も奥山も、これまでに我々が経験したことのないほどの環境の荒廃を目の当たりにしておりますが、その原因の多くは、自然環境の法則を無視した力任せの現代土木造作がきっかけとなる例があまりにも多い中、こうしたコンクリートを用いた車道造りにおいても、きちんと大地をケアして土中の通気浸透環境を全く痛めずにむしろよりよく改善し、土地の環境と一体化させてゆく方法があることも伝えていかねばなりません。
今回、そんな施工の一例を少しご紹介いたします。

駐車場に敷き詰めるコンクリート盤は一枚の重量約500㎏、長さ4m、これを組み合わせて敷きつめていきます。
ただ単に敷くわけではなく、コンクリート盤や車の重量が大地を圧迫して土中の生物活動を妨げず、さらには下地土壌の通気性、浸透性を損なわないような下地造りをしていきます。
写真は、平板を敷く下地に焼いた杭を打ち込みます。1枚に対して3か所杭を打ち、これに菌糸や根を絡ませて、平板の重量を支える構造をとります。

材料となるコンクリート盤及び、焼き杭。杭は表面がうろこ模様になるまで十分に炭化させます。
つまり、炭の棒が土中でコンクリートの重量を支えるのです。
今回、車道と駐車場面積合わせて約160平方メートルに対し、200本近くの杭を打ち込んでいます。
ちなみに、今回用いたこの巨大なコンクリート盤も、実は再生利用です。

さらに、コンクリート盤の下に土中菌糸や樹木根を誘導する、通気浸透孔を開けていきます。
この駐車場でやはり、200か所程度の通気浸透孔を設けました。

その穴には、炭と剪定枝を絡ませて、その分解に伴って増殖する菌類微生物の活動によって、さらに、建築工事に伴う締固めで傷んでしまった土地の改善を促していきます。
上にかぶせて行くコンクリート盤は、この通気浸透孔をブリッジ状の構造で守るのです。

そして、コンクリート盤をそっと置いていきます。

コンクリート盤の目地部分に、砕いたコンクリート片をコツコツと突き込んでゆくことで、全体を一体化して重量を受け、車の重量負荷を分散させます。

そのための大切な材料となるコンクリート片は、以前に他の現場で解体したU字溝やコンクリートブロックなどを砕いて用います。
環境の再生はすべて、有機物と無機物の循環です。自然界の循環がそうであるように、何も捨てずに組み替えて利用してゆく、それが良い環境を作ってゆくために最も大切な考え方かもしれません。
スクラップ&ビルドの時代を早く脱却して、健康な大地を軸にしたすべての循環、そんな時代の到来を夢見ます。

そしてさらに、駐車場のアクセントおよび車道部分はコンクリート舗装になりますが、その型枠設置後です。
この下地造りが大地環境の健全化のために重要な作業となります。我々はそんな見えない部分に時間と労力を注ぐことで、どんな場所でも人によっても木々にとっても、そして訪れる虫や鳥たちにとっても心地よい環境へと育ててゆくのです。

そしてまた、下地に焼き杭を打ち込んでいきます。

杭は下地地面より6センチほど高くし、この高さで鉄筋メッシュを載せていきます。

そしてまた、下地に数か所ほど通気浸透孔を設けて竹炭、枝粗朶を挿入します。

そしてまた、下地への荷重を点状に支えて大地を圧迫しないように、解体廃材をこぶし大に砕いてそれを下地材に用います。

コンクリート下地、ワイヤーメッシュ敷設後。
焼き杭によってコンクリートを支える構造で、下地には砕いたコンクリート片、レンガ廃材、ウッドチップ、炭、そして細い竹も入れています。空間を保つのに、有機物と無機物を組み合わせすのです。
竹は、昔、鉄筋の代わりに竹を用いていた時期や地域や国があったようですが、昔の小舞下地壁がそうであるように弾力があり、環境上も機能的にも、いずれ劣化してゆく鉄筋に比しても非常に有効だと実感し、下地に積極的に用いております。

通気を妨げず、自然界において石がかぶさったような状況を作ってゆくことで、心地よく呼吸する駐車場になっていきます。

車道も同様に、すべての水がきちんと大地に吸い込まれて微生物によって浄化されていのちのエネルギーへと帰してゆくよう、丁寧に下地を造作していきます。
見えない部分ですが、心地よく育ってゆく環境つくりのためにここが最も大切な部分なのです。

そして一区画ずつ、コンクリート打設します。

車道部分のコンクリート敷き均し後。

そして、コンクリートが硬化する前に表面を洗い出して小石をごつごつと浮き出させます。
これも、傾斜のある車道で降った雨が加速度を付けて流れることなく、目地から浸み込んでゆくための配慮と同時に、滑りにくいようにといった具合の人の使い勝手への配慮、さらには見た目の落ち着きをも、両立させてゆくのです。

見た目は何の変哲もないコンクリート車道ですが、ここに降った雨は全て浸透して土地を潤していき、そして呼吸して心地よい環境を保ってくれる、そんな駐車場になりました。
建築工事中はちょっとした雨でも泥水が流亡していたのですが、こうして車道完成後、先日の台風でも大雨でも、まったく泥水の流亡はありません。
また、こうして土壌の通気浸透性が高まれば、周辺土壌もまた、さらに膨軟に良い状態へと変わっていきます。こうして土地は自然の働きによって再生されるものであり、私たちの造作は自然環境が自ら再生しやすいように、きっかけを作るにすぎません。逆に言えば、それだけでよいのです。すべてを人がやろうとしても、自然の働きには全く及ばないのですから。
そして、建築工事に伴っていたんだ木々も、精気を取り戻してきたように感じています。
見えない土中の環境つくりの作業を理解してくださり、徹底的に改善させてくださいましたお施主のAさん、どうもありがとうございました。
人の造作が環境をよい方向に変えてゆく、それが本当の人のあり方であってそこにしか、持続可能な未来はありません。
私の仕事はますます、こうした住環境ばかりでなく、里山奥山を含めた環境全体の再生の依頼が非常に増えてきました。
街だろうが山だろうが、どこにおいても、息づく大地を保つこと、環境を豊かに健康に保つということはそれに尽きると言っても過言はないでしょう。
私たちは大地の上で自然の法則の中、すべての循環の中でしか生きられない、それが厳然たる真理、そのために、そしてそのことを伝えるために、今年後半も全力で生きていきたいと思います。
お盆明けもどうぞよろしくお願いいたします。皆様ありがとうございました。
投稿者 株式会社高田造園設計事務所 | PermaLink
埼玉県飯能市の庭、竣工 2018年4月13日

新緑まぶしいこの時期、あらゆる命にとって一年の中でも最も希望に満ち溢れる時期ではないでしょうか。
この時期を新学期、新年度のスタートとしてきた日本人の感性に、心地よい親しみを感じます。
さて、この一週間、泊まり込みでの集中施工で庭が完成し、また一つ、これから育まれる風景が生まれました。
入間川の畔、背面の崖線の木々が借景となって繋がってゆく、そんな風景を意識しました。

この庭の正面に、地元の憩いの場であると同時に週末にはたくさんの観光客でにぎわう飯能河原のゆったりした景が広がります。
庭の背景として絶好のロケーションであると同時に、この庭が飯能河原の一角の風景として、訪れる人たちにとっても、さりげなく、飯能河原の心地よい印象を深めてもらえる、そんな庭を心がけました。

家屋側、玄関付近からの景。飯能河原周辺の森とつながってゆく、そんな植栽と空間配置です。

この住まいのデッキからの眺めを構成する、その中で改めて、風景はせせこましい人間の所有を超えてつながっているという、ごく当たり前のことに気づかされます。
風景ではなく、環境のつながりというのが本来なのでしょう。
庭を想うことで、生きとし生けるすべてのいのちのつながりに想いを抱く、そんなきっかけになる庭つくりができれば、そんな気持ちになります。

こじんまりとした平屋、この場所にはこのスケールがたまらぬほどにしっくりと収まります。
これが二階家屋であれば、背面段丘崖の木々とのつながりがぷっつりと途絶えてしまうのです。

庭の木々越しの家屋風景。植えたばかりの木々も、植えられた直後からその土地の風景に何の違和感もなく溶け込む、そんな植栽の在り方が、数十年の風景を育むものと信じます。

道路から見た庭の全景。
単純で一見何もない、シンプル極まりない空間ですが、周辺の景に違和感なく収まり、そしてこの地の風情をさらに高めてゆく、それが私立ちの目指す庭の極意かもしれません。

庭の木々と背面段丘の木々。

シンプルでいい。その土地の風景として、人間だけでなく、あらゆる命にとって心地よく愛される庭、そんな空間を作っていければ、造園という仕事は本当に今の時代にかけがえのない価値を発揮することでしょう。
お施主のIさん、施工まで長らくお待ちいただきありがとうございました。
また、今もなお、お待ちくださっているお客様、一つ一つ心込めて作ってまいりますので、今後ともどうかよろしくお願いいたします。
投稿者 株式会社高田造園設計事務所 | PermaLink
取手の庭の竣工と、ダーチャ畑の植え付け 平成30年3月16日

時の流れは待ったなしの速さで、つい最近、寒が明けて旧正月を迎えたかと思ったら、もうすでに春分を迎える頃となりました。
高田造園も西に東に奔走する中、最近の日常を少し紹介したいと思います。
まずは数日前に竣工した、茨城県取手市の屋外環境を少しばかり紹介します。
ここは数年前の河川氾濫の記憶新しい小貝川流域、県のハザードマップ浸水想定地域に接する土地です。
建築工事に伴う盛土、造成によって土地の通気浸透環境はますます荒廃し、土壌環境は悪化し、敷地にはあちこち水たまりができては長く解消せず、またもともとあった木々も枯れたり弱ったり、そんな状況の改善からスタートしました。
完成後の今、庭も駐車場も雨水はすべて円滑に浸透して土中を潤す、そんないのちの循環が再生されました。

これが駐車場と主庭、施工前の状態です。

施工後。
駐車場から主庭に、菜園側には木々の間を抜けて伝います。

主庭、菜園脇の木々の合間のベンチ

雑木林に面した中庭側は、雨落ちの浸透処理と窓際の近景植栽といった、ごく控えめな造作にとどめて、心地よい多目的スペースとして残します。

主庭の施工前。

主庭施工後、南庭デッキ前。
ここでは、玄関前以外はすべて雨どいを設けることなく、屋根の水は雨落ちの溝に浸透し、土中の菌類微生物活動によって大地のエネルギーに還元されて潤してゆく、そしてこの土地の土壌環境は日に日に豊かに育ってゆきます。

表土の通気浸透改善施工中。
雨落ち部分だけでなく、樹木植栽マウンドを中心に、ネットワーク状に横溝浸透ラインを掘っていきます。
ここは炭と枝葉を絡ませて、発生する菌糸の働きによって植栽樹木の根系もまたネットワークのように広く深く張り巡らせて、表土の状態を豊かに快適に育ててゆくのです。

道路に面した東側は、家際の植栽と外周植栽、そしてその間の園路を連続させていきます。

あとひと月もすれば木々は芽吹き、清らかな新緑の光に家屋は包み込まれることでしょう。
生まれたての庭、これから月日とともに、環境、人、共に豊かに育ってゆく、竣工したての住まいの環境に、そんな想いを込めます。

さて、3月となると、ダーチャフィールド自給菜園の植え付け作業も始まります。
ひと工事を終えてほっと一息つく一時に、こうした楽しい作業を進めます。

この日はジャガイモの種芋のほか、春大根に小松菜を植えます。

植え付け後、複合発酵バイオ資材ともみ殻燻炭を、表層に重ねてまぶしていきます。

その上に、稲わらによって表層を保護していきます。適度な蒸発調整と、菌類微生物による表土の改善効果の高さゆえに、稲わらはマルチ素材として他に代えることのできない価値があります。

稲わらマルチ後、麻ひもを張ってわらの飛散を止めていきます。

黒いラインは灌水チューブです。このチューブで、当社で培養している複合発酵酵素水をじわじわと大地に浸み込ませていきます。
浸み込んで大地のエネルギーと化してゆく水の動きを見ていると、それだけでうれしく豊かな心持になります。
今回、わずか30坪足らずの畑植え付けに、5人で半日かけて丁寧に行います。収穫を経済ベースで販売すれば当然、この日の日当すら出ません。
そこが、これからの農への向かい方を問い直す機会となるように感じます。
このダーチャフィールドの菜園面積は合計約50坪、収穫を市場価格のお金に換算すれば、それこそ採算など全く及ばないものですが、自給的な暮らしのために、この畑を循環させてうまく使えば、たったこれだけで一家庭でつつましやかに消費する野菜根菜のほとんどが自給できる、セーフティーネットになるのです。
かつての暮らしにおいて、世界中の人が、そんな豊かな餌場を大地に保ち育ててきた、そんな営みの積み重ねの上に今があります。
その大地の豊かさを、一時の経済の犠牲にせずに後世に伝えてゆく、その鍵は、こうした半自給的な楽しみと、そこで育まれる確かな感覚の中にこそ、あるような気がしてなりません。
投稿者 株式会社高田造園設計事務所 | PermaLink
新年、最初の庭竣工「野鳥の集う庭」 2018年1月31日
今年も早、立春を迎えとしています。
今年が平和と希望の年になりますように、祈りを込めて。

今年最初の造園環境改善工事、千葉市若葉区の新興住宅地の庭が先日竣工しました。
この住宅造成地は、私の地元、森を切り払い、畑をつぶし、重機で平らに造成し、幾世代にも続く故郷の原風景も、生き物の生育環境も大規模に潰して、造成されました。
心のふるさと、地元の森や畑が大きな機械力ではぎとられるように造成の始まった、数年前のやるせない気持ち、今も浮かびます。
それまであった森や畑、古い家、すべてをはぎとり平らにして立ち並ぶ新たな家屋、そこに住居を構えられたOさんに、庭つくりの依頼をいただいたのです。
野鳥の写真を撮り続けてきたOさん、建築前の打ち合わせの際に私に言いました。
「たくさんの野鳥が訪れ、住み着き、森に行かなくてもここで野鳥観察ができる、そんな庭にして欲しい」
というものでした。

昨年の9月に始まった工事は2期に分けて行いました。大規模に地形を壊して行う最近の住宅開発地の多くは、風を緩和してくれる樹林もなく、強風の砂漠のような無機質な、そんな暮らしの場に変貌します。
ここに自然環境を再生する意味を考えます。
過去永劫に育てられてきたいのちの環境を現代一時の間にすべてを奪い取って顧みない、それが現代のわれわれ人間のやっている所業。
しかし、そこに心あるお施主が居て、そして、庭を野鳥が集う森にしたいと要望されたとき、
「ああ、この砂漠のような住宅地に一点でも、生きた土地、森が育つ環境を再生していけば、やがてそこが点々と森をつなげていって、街の環境再生の起点になって行くかもしれない。」
そんな希望が胸によぎり、そしてこの庭環境再生に取り組みました。

畑と林だったつい10年前、この辺りの森にふつうにあった木々を組み合わせて一群落を構成して、広大な住宅地にわずか一か所の植え込みが、街の見え方を大きく変えていきます。

一期工事にて、玄関前の植栽、アプローチ、浸透する駐車スペースの施工を終え、そして今年になって二期工事にかかり、先週完了したのです。

庭の中央には枯掘りのような溝を巡らせて、そこが傷んだ大地の呼吸再生の要になります。
枯れ流れのような日本庭園における造形造作も、本来はその場の環境を息づかせていのちの環境をより豊かに育むための環境装置という面が必ずありました。
失われた先人の智慧、環境を保つ技を、庭の中で未来の人たちに繋いでゆく役目、現代の造園の中で、それを担わなければいけません。
野鳥が集う庭、それは、単に特定の野鳥が好む実を植えたり巣箱や水場をつければよいというものでは決してありません。
土の中の世界を含めてたくさんのいのちの循環がことのできる、豊かな環境を取り戻し、そしてその優しく温かな木の流れの中で、小鳥たちもここで安らげ、いのちの気配に安心するような、そんな環境にしてゆくこと、そこが大切なことと思います。

小鳥が憩う水場は、浅い水盤を用います。
この水盤の下の土の中に大きな空洞を設け、土中の空気と水を動かしてゆく拠点になります。
見える造作よりも、土の中の見えない部分の造作に、より多くの配慮を注ぐことで、いのちの気配溢れる心地よい環境が醸成されていきます。
お施主のOさんは、庭にルリビタキを呼ぶのが望みです。
ルリビタキはなかなか街の中の庭には訪れませんが、おそらく、何年かすれば、きっとこの庭にルリビタキも来てくれることでしょう。
小鳥たちのための庭、この庭がそうなるように、今後も管理育成していきます。

玄関前の石畳。この周辺の植栽も含めて、昨年秋の竣工です。すでにしっとりと、土壌が育っていることが様々感じられます。
造成され、むき出しの赤土だった、痛々しい環境に、丁寧に向き合うことで再び、森の木霊たちが戻ってくる、そんな実感。

植え込みの土壌保護のためのウッドチップマルチも、呼吸する土の上で絡み合い、飛散することなく落ち着き、そしてそこに菌糸のネットワークが張り巡らせます。
この菌糸が様々ないのちを繋ぎ、生と死を繋ぎ、大地のいのちの連携をつくり、そして環境をゆっくりと豊かに育ててゆくのです。
植栽仕上げ後、わずか二か月で、こうした状態に至る、そのために、我々は土の中の環境再生に力を注ぐのです。

2か月前に植えた樹木の根を彫り上げてみると、すでにびっしりと粘菌、変形菌がまるで血管のように大地のネットワークと木々の根をつなげようと、活発に動いていることが分かります。
これを確認してはじめて、私たちの造園施工は完了です。
木々も人も、動物、小鳥たち虫たち、菌類微生物、あらゆる命が平和に共存する世界、そんな理想を庭に込めるのです。
この庭は、これから生き生きと育ってゆくことでしょう。
お施主のOさん、長らくありがとうございました。
また、お待たせしておりますお客様、心機一転、今年はこれまでにましてさらに良い空間を提供してまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。
皆様、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿者 株式会社高田造園設計事務所 | PermaLink